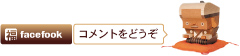工芸はモヤモヤ。
明治政府による制度的な工芸と美術の区別は、
簡単にいうと外人さんに説明するために、もしくは話を合わせるために行なわれました。
当時、襖絵や掛け軸や屏風、書、茶道具、簪、根付けにその他もろもろ、
今では工芸や彫刻、絵画、デザインなどと分類されるそれらを、
どう分類し説明すればいいのか誰にも分からなかったのです。
ましてそれらを総称する言葉は存在しなかったし、その必要もなかったのでしょう。
「近代以前には、ひとことで造形芸術(美術や工芸)を意味する言葉がなかった。」
訳ですが、必要に迫られる時がきました。
それは1873年に日本政府が初めて公式参加するウィーン万国博に出品するにあたり、
1872年(明治5年)に同博の出品分類(ドイツ語)の翻訳として「美術」という言葉が生まれ、
「西洋ニテ音楽、画学、像ヲ作ル術、諸学等ヲ美術ト云フ」と定義されました。
漢字が苦手なぼくにはよく分かりませんが、像を作る術?おまけに諸学ですから、
とにかく何でもありってことで、もちろん工芸もこれに含まれています。
黒船襲来で江戸から明治で文明開化、一気に洋式化される中で
日本美術も西洋美術の枠組みに合わせて再編成されます。
「西洋の鋳型に日本をはめ込むといえば、油絵や洋館の移植が想起されるかもしれないが、
実際にはそうしたもともと日本にその伝統がない分野の移植は、
西洋を日本の風土に馴染ませる努力をしたにすぎない。
むしろ厄介だったのは、日本画、工芸品、社寺建築など伝統分野の方で、
それらを西洋化するためには、西洋化されてもそれらのアイデンティティが失われないために、
それらの芸術的高尚さを対外的に認知させる努力が不可欠だった。
具体的には、一方では日本美術の固有性が揚げられる必要があったし、
もう一方では、江戸時代までに培われてきた『造形芸術』が、
西洋流の〈美術〉、〈工芸〉、〈工業〉といった概念によって
腑分けされなければならなかったのである。」
油絵を洋画といって、その遠近法などを真似ることよりも、
襖や屏風に描かれていた絵を日本画と称して額に納めるのには、
大変な努力や苦労があったでしょうし、
数多ある造形物の何を工芸とするのか、
陶器一つとって見てもその中で、これは工芸品、これは工業品と分けることは、
不可能に近い困難だった違いありません。(未だよく分かりませんが)
しかも西洋の方式に合わせながらも、戦争の世紀へと富国強兵の只中、
外国の方々に日本てすげーんだぞと威勢を張り、
日本のアイデンティティを主張しなくちゃいけない時代でもありました。
そんなこんなするうちに、
「『工芸』は1890年頃に定着した言葉です。」ということになった訳です。
長い年月を掛けて培われてきた「いろいろ」を文明の力でもって突貫工事、
夏季は高温多湿の日本の風土にレンガでできた洋館を建てちゃ、カビも生えるってもんです。
結果、美術も工芸も「モヤモヤ」しちゃって、カビが生えないように美術館で保存し、
芸術の秋なんてなキャンペーンでもってご覧頂くほかないという、
なんともマニアックな業界になりました。
工芸(美術も)自体がモヤモヤと曖昧なまま存在し、
その中で表現者もモヤモヤと曖昧なまま作品を発表しているといった事態です。
美術や工芸になにやら難しいものという印象をお持ちの方がいるとすれば、
それは「難しい」のではなく「モヤモヤ」としたものというほかないのです。
樋田豊次郎著『工芸の領分』には工芸家として読むと、
まだまだ興味深い話が沢山書かれています。
工芸をしてる人はもちろん、したい人、好きな人にはおすすめの名著です。
ぼく自身ことあるごとに読み返し、付せんベタベタで、これほど線を引いた本は他にないです。
ただ、2900円(税別)と少々高めなので、
ぼくが気になった所をもうちょいピックアップしたいと思います。